前回の記事を投稿した後、1ヶ月以上、新しい記事を投稿しなかったので、また放置かと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、古い記事の修正作業(主にウェブ地図の置換作業)を行っていたり、ある種の調査を行っていました。
とくに、京都府周辺に設置された三角点の古い「点の記」に目を通し、その三角点が設置された地域や山の「俗称」を調べた成果については、「京都府の山」の市町村別最高峰は? / 皆子山を遠望する の記事に追記しておきましたが、この記事はただでさえ追記やら補足やらが多く、そろそろ見づらく感じてきましたので、当該部分のみ、こちらの記事に移しておきます。
その話と合わせ、記事の後半に過去の山行記録を。
目次
京都の山の俗称(「点の記」より)
なかなか捗りませんが、古い「点の記」で確認できる俗称・旧称を調査しています。
「点の記」には所在地の「俗称」が併記されていることがあり、それら「俗称」は、おおむね現在の山名や、あるいは既知の旧名、または当時の大字や小字と一致しますが、稀にそうではない場合があります。
そういった 例外のみ ピックアップしてリスト化しています。
すでに失われたと考えられる「俗称」は、きわめて局地的に用いられていた呼称も含まれていると考えられ、広域的に認識されていたかどうかは分かりません。
また、必ずしも「正しい」(正確である)とは限らず、そのように呼ばれていた可能性がある、という程度です。
以下の表における「点の所在地」は、三角点が行政界上と思わしき地点に所在する場合であっても、「点の記」が「所在地」とする住所地名を優先しています。
あくまでも「点の所在地」であり、三角点が設置される山の所在地ではありません。
スマートフォンの表示に対応していますが、幅が広い横画面のほうが見やすいでしょう。
京都市
京都市。
| 現在の山名 | 俗称 | 基準点名 | 標高値 | 点の所在地 所在地の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 灰屋山 | 塔ノ峠 | 三等三角点「宮」 | 732.7m | 京都市右京区 京北灰屋町の西 |
| 1890年(明治23年)観測時の「点の記」に「備考 塔ノ峠ノ頂上」「俗稱 塔ノ峠」とある。 | ||||
| 三頭山 | 地蔵山 | 三等三角点「細野」 | 727.8m | 京都市右京区 廻り田池の北東 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 地蔵山」とある。 | ||||
| 地蔵山 | 猿坂山 | 一等三角点「地蔵山」 | 947.2m | 京都市右京区 嵯峨樒原の東 |
| 1886年(明治19年)観測時の「点の記」に「俗稱 猿坂山」とある。 | ||||
| 峰山 | 城ヶ峯 | 三等三角点「峰山」 | 537.2m | 京都市右京区 高山寺の北 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 城ヶ峯」とある。 | ||||
| 長尾山 (京見山) | 朝原山 | 三等三角点「嵯峨」 | 295.7m | 京都市右京区 大覚寺の北 菖蒲谷池の東 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 朝原山」とある。付近の「音戸山(音頭山)」や「仁和寺長尾山」、「嵯峨富士(遍照寺山)」との混同が見られる。この話は当サイトの他記事 でも。 | ||||
| 釈迦谷山 | ノノゲン山 | 三等三角点「釈迦谷山」 | 290.7m | 京都市北区 鷹峯の北 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 ノノゲン山」とある。この話は当サイトの他記事 でも。 |
||||
| 音羽山 | 惣山 (惣谷山) | 三等三角点「小山」 | 593.0m | 京都市山科区 逢坂関の南 牛尾観音の北東 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 惣谷山」とあるが、「谷」の字が二重線で消されている。この話は当サイトの他記事 でも。 | ||||
| 西野山 (二石山) | 惣山 | 三等三角点「西野山」 | 238.9m | 京都市山科区 稲荷山の東 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 惣山」とある。「惣山」が入会山の意味かは不明。点名の「西野山」は所在地名であって山名ではないが、現称として定着した。西麓の深草村からは「二石山」、東麓の西野山村や南麓の勧修寺村からは「大日山」と呼ばれていた可能性が高い。 | ||||
| 山上ヶ峰 (北松尾山) | カヤオ尾 | 三等三角点「上山田」 | 482.0m | 京都市西京区 JR保津峡駅の南東 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 カヤオ尾」とある。この話は当サイトの他記事 でも。 | ||||
| (現称不明) | 下陣林山 | 三等三角点「御陵」 | 186.7m | 京都市西京区 京都大学 桂キャンパスの北西 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 下陣林山」とある。桂坂地区の宅地造成に伴い、1989年(平成元年)に移設しており、当初の選点地点(下陣林山)は山としては消失。現在の三角点所在地は峰ヶ堂城跡・法華山寺跡比定地。 | ||||
| 大暑山 | イチゴ(?) | 三等三角点「大原野」 | 567.5m | 京都市西京区 西山団地の南 小塩山の北東 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「備考 大原野山ト云フ山ノ上ニアリ」「俗稱 イチゴ」とある。「イナゴ」かも? 俗称は縦線で修正して書き直されている。大暑山は戦後に創作された俗称に過ぎず、本来は山名として論じるに値しない。 | ||||
京都府南部
宇治市、八幡市、向日市、長岡京市以南。いわゆる山城地域。
| 現在の山名 | 俗称 | 基準点名 | 標高値 | 点の所在地 所在地の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 五雲峰 | カラカサ松 | 三等三角点「菟道」 | 341.6m | 宇治市 日清都CC内 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 カラカサ松」とある。当初、三角点は五雲峰に設置されたが、1984年(昭和59年)、現在地に移設された。よってカラカサ松は現在の五雲峰。 | ||||
| 仏徳山 (大吉山) | 旭山 | 三等三角点「旭山」 | 131.5m | 宇治市 興聖寺の北 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 旭山」とある。現在の「朝日山」は仏徳山の南東の山。この話は当サイトの他記事 に詳しい。 | ||||
| 釈迦岳 (釈迦ヶ岳) | 釋迦ヶ岳 | 一等三角点「鷲峰山」 | 680.9m | 綴喜郡宇治田原町 金胎寺の北東 |
| 1886年(明治19年)観測時の「点の記」に「釋迦ヶ岳ノ西頂 但シ著名ナル鷲峯山ニ接近ス因テ本點ノ名稱トス」とある。「釋迦ヶ岳ノ西頂」なので、本来の釈迦ヶ岳は一等三角点のすぐ東の小ピークを指す可能性がある。この話は当サイトの他記事 に詳しい。 | ||||
| 艮山 | ヤッキョウ | 三等三角点「弥谷原」 | 443.6m | 綴喜郡宇治田原町 大正池の北 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 ヤッキョウ」とある。 | ||||
| 奥岸谷山 | センジン | 三等三角点「腰越谷」 | 521.7m | 相楽郡和束町 犬打峠の西 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 センジン」とある。 | ||||
| (現称不明) | シンワリ | 三等三角点「車谷」 | 201.7m | 木津川市 蟹満寺の東 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 シンワリ」とある。 | ||||
| 大野山 | 相場取 | 三等三角点「大野」 | 203.7m | 木津川市 JR加茂駅の西 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 相場取」とある。未知の相場山(旗振山)か? | ||||
| 御本陣山 | 御本寺山 | 三等三角点「岩舟」 | 320.9m | 木津川市 岩船寺 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 御本寺山」とある。 | ||||
| 笠置山三角点 | ヲハゲ | 三等三角点「笠置山」 | 323.8m | 相楽郡笠置町 かさぎGCと隣接 |
| 1889年(明治22年)観測時の「点の記」に「備考 土人称シテ笠置山ト云フ」「俗稱 ヲハゲ」とある。 | ||||
| (現称不明) | タカノ塚 | 三等三角点「八條敷」 | 348.7m | 相楽郡笠置町 レイクフォレストリゾート ゴルフコースと隣接 |
| 1889年(明治22年)観測時の「点の記」に「俗稱 タカノ塚」とある。点の所在地は笠置町だが南山城村との町村境。 | ||||
京都府中部
丹波地域のうち、亀岡市、南丹市、京丹波町。
| 現在の山名 | 俗称 | 基準点名 | 標高値 | 点の所在地 所在地の目安 |
|---|---|---|---|---|
| (現称不明) | ボウズ山 | 三等三角点「穴太」 | 167.1m | 亀岡市 穴太寺の西 |
| 1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「備考 穴太寺ノ西ノ山ニテ穴太川ノ上ニアリ」「俗稱 ボウズ山」とある。 | ||||
| 嶽山 | 嶺 | 二等三角点「中世木村」 | 557.6m | 南丹市 人尾峠の南西 世木ダムの北 |
| 1889年(明治22年)観測時の「点の記」に「俗稱 嶺」とある。 | ||||
| 品谷山 | 首杉? ↓ 品谷山 | 二等三角点「佐々里村」 | 880.6m | 南丹市 ダンノ峠の西 |
| 1888年(明治21年)観測時の「点の記」に「○俗首杉ト称ス」とあるが(○は読めず)、1977年(昭和52年)更新時の「点の記」で「俗称 品谷山」と改めている。 | ||||
| ブナノ木峠 (ブナノキ峠) | 七七瀬谷ノ頭 | 三等三角点「芦生」 | 939.0m | 南丹市 京都大学芦生研究林内 |
| 1889年(明治23年)観測時の「点の記」に「俗稱 七七瀬谷ノ頭」とある。 | ||||
| シンコボ | シンコヲボウ | 三等三角点「永谷」 | 811.3m | 福井県大飯郡おおい町 若丹国境杉尾坂の東 |
| 1889年(明治23年)観測時の「点の記」に「俗稱 シンコヲボウ」とある。 | ||||
京都府北部
福知山市、綾部市、舞鶴市、与謝野町、宮津市、京丹後市、伊根町。
丹後地域+福知山+綾部。
| 現在の山名 | 俗称 | 基準点名 | 標高値 | 点の所在地 所在地の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 上殿 (霊山) | 城前 | 二等三角点「上川合」 | 452.8m | 福知山市 須知山トンネルの南西 |
| 1889年(明治22年)観測時の「点の記」に「俗稱 城前」とある。俗称「城前(ジョウゼン)」の音読みは現称「上殿(ジョウデン)」の音や旧称「霊山(リョウゼン)」の音とも通じる。点名「上川合」は2点あるが北側。 | ||||
| (現称不明) | 井根山 | 三等三角点「堀山」 | 141.4m | 福知山市 福知山駅の南東 平和墓地の山 |
| 1891年(明治24年)観測時の「点の記」に「俗稱 井根山」とある。 | ||||
| 頭巾山 | 銅巾山 ↓ 頭巾山 | 二等三角点「納田終村」 | 870.8m | 福井県大飯郡おおい町 若丹国境尾根 |
| 1888年(明治21年)観測時の「点の記」に「俗稱 銅巾山」とあるが、1977年(昭和52年)更新時の「点の記」で「俗称 頭巾山」と改めている。 | ||||
調査中。
現在は福知山市のうちJR福知山駅以南は済。
艮山~大正池ハイキング
2009年(平成21年)11月末に綴喜郡井手町と宇治田原町の町境に所在する艮山(うしとらやま)を他の方と登山した際に撮影した写真を掲載しておきます。
上のリストに艮山の名前が挙がっているので、今回、わざわざ引っ張り出してきました。
この年(2009年)は丑年で、寅年を迎えるにあたり、丑年の終わりに「ウシトラ山」を駄洒落で訪れたように記憶しています。
ですが、年の暮れまで待つと紅葉が終わってしまうので、11月末を選んだようです。
その頃は新元号となっているでしょうが、干支が一回りする2021年末に、同様のことを考える方がいらっしゃるかもしれませんね。
当時の山行記録によると、城陽市に所在するJR奈良線の山城青谷駅を起点として、粟神社~藪をかき分けて旧林道~鏡谷山(標高点176m)~四等三角点「二ノ頭後」(標高288.2m)~高雄山(標高点443m)~艮山(標高443.7m)と縦走し、大正池へ下り、その後、「龍王の滝」や、俗に「万灯呂山展望台」とも呼ばれる大峰(標高点303m)へ立ち寄って帰りました。
(※標高値は2019年(平成31年)2月時点の値であり、2009年(平成21年)当時の値ではありません)
厳密に申し上げれば、ピークハントのため、鏡谷山の北東0.5km地点に所在する高塚山(標高点202m)にもわざわざ先に寄り道しており、尾根伝いの縦走とは言えません。
この周辺で、地形図に山名が表示される飯盛山(標高点183m)や高塚山(標高点223m)とは別に、(2009年当時は、)すぐ付近の標高点162m峰も「飯盛山」、標高点202m峰も「高塚山」とする山名標が設置されており、それぞれ2座ずつ所在していましたが、なぜそのような事態となっていたのか分かりません。
また、現況も分かりかねます。
茶うす山が消えます(城陽市・井手町の茶𥓙山)
2009年(平成21年)当時、市辺からの縦走路として、市辺~茶うす山~鏡谷山~二ノ頭後~のコースを選ぶ手もありました。
「ありました」と過去形なのは、新名神高速道路の建設工事に伴い、その全通を見越して新設される工業団地(京都山城白坂テクノパーク)の整備事業で切り開かれ、「茶うす山」周辺の丘陵は消滅することが決まっているからで、2019年(平成31年)現在、すでに下の座標の地点は山としては失われつつあるようです。
「茶うす山」は標高にして100m未満のきわめてマイナな山で、このあたり に所在していました。
「うす」の字は「林」の下に「石」と書く国字「𥓙」で、「うす」「そ」などと読みます(「磨」の漢字から「まだれ」を除いた国字)。
かつては山頂に三等三角点「白阪(しろさか)」も設置されていましたが、これは(おそらく)今回の工事とは関係なく廃点となっています。
まぎらわしいですが、「城陽市市辺白坂(しろざか)」の住所地名と異なり、点名の表記は「白阪」であり、読みも「しろさか」。
もともと、三角点の設置当初は少し西側の地点に設置されており、1908年(明治41年)測図、1912年(明治45年)発行の正式二万分一地形図「郷之口」では標高82.5m。
1922年(大正11年)測図、1925年(大正14年)発行の二万五千分一地形図「田邊」では、三角点の東方に「鑓ヶ谷山」「高塚山」「飯盛山」の山名が連なります。
このうち、鑓ヶ谷山の山名は失われたようですが、城陽市市辺鑓ヶ谷の地名や、あるいは林道鑓ヶ谷線(槍ヶ谷線?)の呼称にその名を留めています(かつて、マンガンと水晶の産地だったらしい)。
また、この当時は青谷川を跨いだ北の基準点103.6mに「天山」の山名が表示され、これは地理院地図に見える標高点104mと考えられますが、天山の山名は失われました。
後に「茶うす山」の山頂に三角点が移設され、1972年(昭和47年)修正、1973年(昭和48年)発行の二万五千分一地形図「田辺」では標高94.2m。
この頃の地形図には「茶𥓙山」の山名が表示されますが、現行の地理院地図では三角点も山名も消えています。
2006年(平成18年)現況調査時の「点の記」では、三角点への歩道状況を「梅林の中を通り、尾根に通じる道を歩く」、三角点周囲の状況を「竹林」としていますが、すでに面影はありません。
ただし、「茶うす山」の名は、今後も住所地名としては山麓の地に残ります(北西麓にあたる城陽市市辺茶うす山)(西麓は綴喜郡井手町多賀茶臼塚)。
以下に掲載する写真について。
いずれも撮影月は2009年(平成21年)11月であり、現状を正しく表していない可能性があります。
今後、このあたりの山々も、少しずつ姿を変えていくことになるかもしれません。
常々申し上げていますが、何事に限らず、残るものもあれば、消えるものもあります。
消えるものについては、誰かが記録を残しておけば、それが後世に繋がることもあるでしょう。
紅葉する粟神社 城陽市

紅葉する粟神社さん。京都府城陽市市辺。
1908年(明治41年)の『山城綴喜郡誌』に「祭神の考證未だ正確なるものを得ず、古記に據(よ)れば、少名產名と錄せり。」とありますが、少彦名命を祭神とする説は「古記」によるもので、過去の史料や式内社の祭神考証に記載がなく、正確な祭神は不詳とされます [1]。
また、『山城綴喜郡誌』には、上古、市辺集落には鎮守神社があり、祭神を市辺といい、またオシハというが、恐らくは市辺押磐皇子(いちのへのおしはのみこ)(いちのべのおしわのおうじ)であろうといった話も見えます。
山麓に鎮座する静かな神社さん。
この当時、不即位天皇 [2]として知られる飯豊青皇女(いいとよあをのひめみこ)(いいとよあおのおうじょ)について学んでいたこともあり、ぜひとも参拝したい神社さんでした。
飯豊青皇女は履中天皇の皇女とする説と、履中天皇の皇子である市辺押磐皇子の娘(つまり、履中天皇の孫)とする説があります(それぞれ別人で、2人ともいた、とする説も)。
城陽市市辺は市辺押磐皇子の2人の皇子(後の仁賢天皇と顕宗天皇)ゆかりの地とされ、粟神社の名前や青の地名も、2人の皇子の姉、あるいは叔母にあたる飯豊青皇女にちなむとする説があります(が、どうやら当説は今ひとつ知名度が低いようです)。
この話は日本における青銅の歴史にまで通じていますが、興味がある方も少ないでしょうから、さすがに割愛します。
三角点「二ノ頭後」 綴喜郡井手町

四等三角点「二ノ頭後(にのずご)」。京都府綴喜郡井手町。
標高288.2m。(→「測地成果2024」により、288.1mと改定)
今回の記事では三角点に話を絞っていますが、高雄山と艮山の間に城陽市最高点が所在します(縦走路からは少しだけ外れています)。
詳しくは、この記事の冒頭でリンクしている「市町村別最高峰」の記事で。
三角点「弥谷原」 綴喜郡井手町・宇治田原町

艮山。三等三角点「弥谷原(やたにばら)」。井手町と宇治田原町の境。
標高443.7m。(→「測地成果2024」により、443.6mと改定)
三角点所在地について、1903年(明治36年)観測時の「点の記」に「俗稱 ヤッキョウ」とあり、明治時代頃にはそのように呼ばれていた可能性があります。
しかしながら、現代においては完全に失われた呼称だと考えられ、「ヤッキョウ」の由来も分かりません。
この「俗称」の成り立ちについて、ご存じの方がいらっしゃったらご連絡ください。
追記しておきますと、本記事をご覧になった方によるものでしょうか、その後、現地に「点名 弥谷原 俗称 ヤッキョウ 山名 艮山」とする山名標が設置されました。
点名の「弥谷原」と俗称の「ヤッキョウ」には「ヤ」の音に共通点があります。
「艮山」を示す現地の山名標

「艮山」を示す現地の山名標。点名の「弥谷原」が併記されています。
2014年(平成26年)4月1日の「三角点の標高成果改定」前ですので、「443.8」の値が示されていますね。
艮山からは宇治田原町の滝の口川へ下ることもできますが、南の大正池へ下るコースもあります。
大正池は艮山の南に所在しますが、踏み跡が明瞭な一般コースとしては、直接、山頂から南の尾根を下るのではなく、山頂から北東の尾根伝いに少し回り込む必要があり、ここが分かりにくいです。
紅葉する大正池と周辺峰の話

カモさんやらアヒルさんやらが多い大正池にて。
大正池の西の標高点373m峰を「片原山」と呼びますが、池の北西の大焼山(二等三角点「多賀」、標高429.2m)や、池の南の有王山(標高点378m)といった、他の大正池周辺峰と異なり、地形図に山名が表示されないため、あまり知名度は高くないようです。(→「測地成果2024」により、二等三角点「多賀」の標高成果は429.1mと改定)
また、池の南東には駒留山(飯盛山)(四等三角点「駒留」、標高474.6m)が所在します。(→「測地成果2024」により、四等三角点「駒留」の標高成果は474.5mと改定)
この山は井手町の最高峰で、計算上、京都府から明石海峡大橋の橋桁を見通せる山ということもあり、過去に現地を訪れて確認していますが、現地の展望状況は今ひとつでした。
大正池は多くの山々に四方を囲まれた山間部に位置しており、それゆえに、1953年(昭和28年)の「南山城水害」で多大な被害を受けた地であることが窺えます。
この「南山城水害」により大正池(旧大正池と旧二の谷池)が決壊し、池の下流にあたる玉川が氾濫。
氾濫による激しい水流や崩落により、巨大な「駒岩」も山から現在地へ押し流されました。
「駒岩」については上の記事で。
下で触れているハンガーノックと「ヒダル神」の話もさわりだけ。
その後、新たに整備されたのが現在の大正池です。

紅葉する大正池。京都府綴喜郡井手町。
大正池は「ため池百選」にも選ばれた美しいダム池です(私たちが訪れた翌年に選定されました)。
上の写真は西岸の浮御堂から撮影したように記憶しています。
…いろいろ書いているうちに思い出してきましたが、この後、長い道のりを経て到着した大峰(万灯呂山展望台)ではハンガーノック(シャリバテ)(英語では”Hitting the wall”)を起こしてしまい、ご一緒していた方に迷惑をお掛けしました。
今回は写真の掲載を見送りますが、万灯呂山展望台は夜景スポットとして知られていますね。
上の記事など、過去に何度か話の種にしていますが、京都府下に何ヶ所かある、大文字の送り火を灯す山でもあります。
艮山(地理院 標準地図)
「艮山(ウシトラヤマ)(うしとらやま)」
標高443.6m(三等三角点「弥谷原」)
京都府綴喜郡井手町、宇治田原町
「粟神社(アワジンジャ)(あわじんじゃ)」
京都府城陽市市辺 付近
脚注
- 突如として現れた「古記」は、いわゆる「椿井文書」(木津文書)の可能性を考慮せざるを得ません。椿井文書は綴喜郡の式内社の捏造に利用されました。[↩]
- 歴代天皇として認められていないが、実質的に即位していたと考えられる天皇。宮内省(→宮内庁)による『陵墓要覧』でも、第十七代履中天皇の皇孫女「飯豊天皇」としており、その陵墓を「埴口丘陵」としています。これが何を意味するか、葬られる陵墓のうち、天皇や皇后は「陵」(御陵)、皇族は「墓」(御墓)と扱いますので、埴口丘「陵(みささぎ))」は、すなわち天皇陵と見なしていることが分かります。『日本書紀』にしたがえば、飯豊青皇女は生涯独身だったと考えられますので、皇后と扱われたわけではありません。[↩]










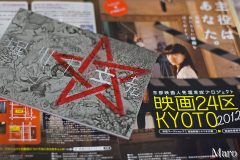



















最近のコメント