昨日、つまり、2015年(平成27年)4月28日は、リハビリがてら上賀茂の深泥池へ。
これからの時期、上賀茂の大田神社さん(大田ノ沢のカキツバタ群落)ではカキツバタ(杜若)が次々とお花を咲かせ、それを目当てに多くの方々が訪れますが、すぐ近くの深泥池でも変わったカキツバタを観賞できます。
かつては葵祭の頃に咲いていたように記憶していますが、(二番花を考慮しても、)ここ数年は花期が早まったと感じます。
目次
深泥池の白いカキツバタ(杜若)

深泥池に咲くカキツバタ(杜若)の白花。
近年になり、白地の花弁に紫色の筋が入る株が増えてきました。
後述するミツガシワの花後や葉も写真に写っており、他の植物とも群落をなしています。
深泥池は暖地としては稀な高層湿原(高位泥炭地)を残していることでも知られます。
湿原の浮島にはまとまったカキツバタ群落がありますが、許可なく近付くことはできません。
池の畔にちらほら咲くお花を近くに眺めるだけでも十分です。
深泥池における、本来は紫色だったカキツバタが白色となり、さらに先祖返り的に紫色の筋が表れる現象は、ベニバナヤマシャクヤクの白花型(白色型)に近いものがあると考えています。
私は植物についてもとくに詳しいわけではなく、ただの推測に過ぎませんが。

深泥池のカキツバタ。白色のお花とつぼみ。紫色が出る。
やや分かりにくいですが、カキツバタの特徴である「黄色いツメ」も見えます。
私はこの白いカキツバタを「京都三珍カキツバタ」の1つとして勝手に選定しています。
残りは平安神宮さんのご神苑に咲く「折鶴」と呼ばれるカキツバタと、ある民家のお庭に自生するカキツバタです。
前者は「雲井の鶴」や「雲上鶴」とも呼ばれるカキツバタの園芸品種で、京都御苑の近くに所在する大聖寺さん(御寺御所)の株を元にして、京都府立植物園にも移植されました。
清浄さや仙境の象徴でもあった「雲に鶴」や「鶴の鳴き声」、「松に鶴」といった組み合わせや、あるいは「夜半に唳く鶴」といったイメージは、古くより詩や歌に詠まれており、『源氏物語』でも取り上げていますが、そもそもは日本でも好まれた白居易(白楽天)の影響があるらしい [1]。
後者のカキツバタについては、今となっては広く知られるようになりましたが、事情があり、私個人としては曖昧な書き方しかできません。
かつて、ご好意により近くで拝見する機会がありましたが、その地に伝わるお話と併せて興味深いものがありました。
深泥池の読みは「みぞろがいけ」「みどろがいけ」?
深泥池の読みは「みぞろがいけ」と「みどろがいけ」、どちらもあり、松ケ崎や上賀茂に住む私の友人や、より年上にあたる世代の方々の間でも読みはまちまちです。
より若い方々の間では「みどろがいけ」のほうが(かなり)優勢でしょうか。
「美度呂池」
在二上賀茂東鞍馬大路傍一
今呼二美曾呂池一『山城名勝志』
正徳元年(1711年)の『山城名勝志』には、「ミトロ池(みどろ池)を今はミソロ池(みぞろ池)と呼ぶ」と見え、江戸時代中期にはどちらの読みも両立していたことが窺えます。
「美度呂池」が古い表記で、「美曾呂池」が新しい表記だと察せられるでしょう。
平安院政期に成立したとされる『今昔物語集』には、いわゆる「鳥の教え」型の説話として「巻第十九 鴨雌見雄死所来出家語第六」が収載されますが、ここでは「美々度呂池」の表記も見え、より古くは「みみどろ池」と呼ばれていた可能性も。
経緯がやや複雑ですが、平安時代末期頃に成立したとされる『和泉式部續集』(和泉式部続集)に、平安時代中期の女性歌人、和泉式部が詠んだ「なをきけばかげだにみえじみどろ池にすむ水鳥のあるぞあやしき」の歌が収載され、ここでは「みどろ池」と見えますので、現存する『今昔物語集』の写本における「美々度呂池」は「美度呂池」の誤りではないかとする指摘もあります(『今昔物語集』も伝本によっては美度呂池としています)。
これも経緯が複雑ですが、菅原道真が編纂した『類聚國史』(類聚国史)が『日本後紀』から引く(『日本後紀』の当該部分は散逸)、平安時代初期の淳和天皇が天長6年(833年)10月に行幸した「泥濘池」も深泥池を指しており、これが史料上で確認できる最古の記録でしょうか。
上代日本語で「泥濘池」は「とろ池」か「どろ池」か見解が分かれるようですが、後世には「登勒池」とも書いたようです。
これは弥勒菩薩が池上に顕現したとする俗説が知られていたからで、ゆえに「御菩薩池」の表記(あて字)も好まれていました。
たとえば、京都市産業部観光課が1937年(昭和12年)に発行した『京都市の史蹟名勝天然紀念物』では「天然紀念物 深泥池水生植物群落(中略)彌勒菩薩が池上に現はれたといふ傳説もある。俗に御菩薩池と謂はれる所以である。」としています。
それが歴史的事実であるかは別として、これを奈良時代の高僧、行基が池を訪れた時の出来事とする書もありますが、いわゆる行基伝説の一種と見るべきでしょうか(行基菩薩にかかる伝説)。
また、岩倉の大雲寺さんの本尊(秘仏)、十一面観音像は行基の作と伝わります(これは後世に撰略された「大雲寺縁起」が詳しい)。
『山城名勝志』における「鞍馬大路」は鞍馬街道を指しています。
「七道ノ辻」の六体地蔵廻り、いわゆる「六地蔵めぐり」のうち、現代では上善寺さんでお祀りされる「鞍馬口地蔵」が、かつては深泥池の畔でお祀りされていたことは知られていますが、鞍馬街道の峠の入り口にあたる深泥池から鞍馬口通(出雲路橋の西方)の上善寺さんに遷されたのも何かの縁というものでしょう。
上で触れた御菩薩池の表記についても、地蔵菩薩を由来とする説との混同が進みました。
鞍馬街道は深泥池のあたりでは府道40号下鴨静原大原線の一部となっています。
米軍は「深泥池」をどう呼んだ?
おまけ的な。
上は米軍による戦後の都市計画図を重ねて表示していますが、「Mizoroga-ike」「MIZOROGAIKE」と表示されていることがお分かりでしょうか。
前者は池の名称を表示しており、後者は地名を表示しています。
池の右下には「NISHI-YAMA 132.5m」、つまり、西山(松ヶ崎西山)も見えますね。
深泥池のミツガシワ

深泥池のミツガシワ(三槲)。咲き残りのお花と花後の様子。
深泥池のミツガシワは氷期(氷河時代)の残存植物(遺存植物)だと考えられています。
ミツガシワは下から上に向かって順々に開花が進むため、上の写真のように、花期が終わる頃にはお花は最上部のみとなります。
例年、池の畔のソメイヨシノが盛りを過ぎる時期にミツガシワが見頃となりやすく。
今から約80年前の記録によると、当時の深泥池には113種もの植物が分布していたそうです。
トキソウ、サワギキョウなどは今でも残存していますが、サギソウなどは失われました。
京都府で新たに絶滅危惧種に指定されたアブノメも、記録によれば、かつては深泥池で見られたようです(が、レッドデータブックを確認する かぎり、府内の分布記録区域に京都市域が含まれておらず、当地からは根絶したと考えられます)。
昔からトンボの宝庫でもあり、小さな小さなハッチョウトンボなどは今も残ります。

深泥池のミツガシワ群生地と水面を埋める桜の花びら。
上の1枚のみ、2012年(平成24年)4月に撮影した写真ですが、参考程度に。
桜吹雪の時期、ミツガシワは上半分がおおむね開花、下半分は散りが進んでいます。
個人的に好きな光景。
余談ながら、複雑な経緯をたどった植物として……。
全国的に見ても珍しい植物のムジナモが、かつて、京都南部の巨椋池から深泥池に移植されましたが、貴重な自生地だった巨椋池は干拓により消滅し、深泥池の株も絶滅しました。
現在の京都府ではムジナモは野生絶滅種の扱いです(巨椋池産の株が今も人為的に栽培され続けている)。
ムジナモはわが國ではほんとうに珍らしい植物で 明治23年5月11日 牧野富太郎博士が江戸川の流域ではじめて発見したモですが その後はどこにも見つけられず 大正14年に京都のおぐらの池で三木茂農学士によつて発見され 三木先生がそれをこの深泥池に移されたのです。そして面白いことには どうしたわけか 今ではおぐらの池にはあまり見出されず かえつて深泥池にたくさん生えています。このモはどこでもあるというものでないので 天然記念物として保護されています。
『植物 珍らしいもの役に立つもの』
『植物 珍らしいもの役に立つもの』は、京都新聞社が学習読み物「サンデー・ブック」として発行したシリーズの一冊で、1950年(昭和25年)に出版されました。
名前が見える「三木茂先生」は、メタセコイアの発見や水草研究で知られる植物学者ですね。
これが発行当時の状況を正しく伝えているのであれば、この頃にはムジナモが「深泥池にたくさん生えていた」らしい。
しかしながら、1948年(昭和23年)に採集された株が、深泥池産としては最後の現存標本で、その後、当地から姿を消しました。
深泥池の裏山(高山)

深泥池と裏山たる標高点179m峰。池には白いカキツバタが咲く。
右上の高い山が高山で、その下の膨らんだ丘陵がチンコ山。
上の写真で右遠方に見えているのが深泥池の裏山たる標高点179m峰で、地形図ではこのあたり 。
この山を越えれば、いわゆる狐子坂(狐坂、きつね坂)や宝が池(宝ヶ池、宝ケ池)です。
この標高点179m峰は、いわゆる松ヶ崎西山(京都五山送り火「妙法」の「妙」の山)の一部とも見なせますが、西山の標高点135m峰や、「妙」の火床が所在する山(約150m小ピーク)より高いため、明確に独立した別個の峰だと感じます。
深泥池からは見えませんが、標高点179m峰のすぐ東にも同等の高さの小ピークが続いています。
その小ピーク周辺の住所地名が京都市左京区松ケ崎高山で、どうやら周辺の山を「高山」と呼ぶようです。
また、179m峰の西、池の内に突き出た半島状(岬状)の丘陵を「チンコ山」と呼ぶとのこと。
せっかくですので、深泥池の外周に沿って整備された遊歩道を散歩しながら、あの山のあたりを目指します。
深泥池の外周をハイキング

深泥池の外周トレイルコースと新緑の裏山ハイク。
深泥池の池そのものは全域が京都市北区に所在しますが、外周から少しでも裏山側に足を踏み入れると左京区となります。
外周部を伝うコースはおおむね歩きやすい山道となっていますが、裏山にあたる松ヶ崎西山や標高点179m峰の山中は立ち入りが禁止されている、あるいは望ましくない地点が多く、地理を把握していない方はメインコースを外れないほうがよいでしょう。
こちらでもあまり詳しく書けません。

裏山の山中にはヤマツツジ(山躑躅)の赤いお花も咲いていました。

深泥池の外周に咲くモチツツジ(黐躑躅)のお花と眩しい緑。
モチツツジはつぼみも目立ちました。
当地に限らず、同等の環境下であればヤマツツジのほうが微妙に花期が早い。
松ヶ崎はミヤコツツジの分布域として知られますが……。
外周コースそのものは、池の北東にあたる京都博愛会病院さん方面へ繋がっています(が、現在は深泥池側からは立入禁止となっています)。
道や取付がやや分かりにくいですが、深泥池からは府道40号を渡り、西の「京銀ふれあいの森」や「大田の小径」の山を登ることもできます。
こちらは上賀茂神社さんにかけて、「本山」と総称される一帯です。
また、高山から西山、狐子坂、林山、東山、城山と東西に連なる松ヶ崎の山塊を「虎ノ背山」(虎の背山)と総称します。
大きな観点で見れば、上賀茂の本山と松ヶ崎の虎ノ背山は山続きとも見なせますが、両者を分けるのが深泥池であり、鞍馬街道といえるでしょう。
狐子坂(狐坂)の話は上の記事で。
深泥池(地理院 標準地図)
「深泥池の裏山」
京都市左京区、北区
脚注
- 日本で流行したのは白居易が作った鶴の詩ですが、用例としては、後漢代の王充による『論衡』藝増篇(芸増篇)に「彼言聲聞於天、見鶴鳴於雲中、從地聽之、度其聲鳴於地、當復聞於天也。」(彼言ふ、声は天に聞こゆと。鶴の雲中に鳴くを見る。地より之を聴けば、其の声の地に鳴るを度(はか)りて、当(まさ)にまた天に聞こゆべきなり。)と見えます。李白による「游泰山六首」の其五に「緬彼鶴上仙、去無雲中跡。」(緬(はる)かに彼(か)の鶴上の仙を思へば、去りて雲中の跡無し。)の対句あり。泰山詩ですので、もちろん道教的な要素が強く。白居易『新楽府』の「五絃彈」(五絃弾)に「夜鶴憶子籠中鳴」とあり。これを踏まえ、『詞華和歌集』(詞花和歌集)に収載される高内侍(高階貴子)の「よるのつるみやこの内にこめられて(はなたれて)子をこひつゝもなき明すかな」をはじめとして、数多くの歌が詠まれました。『源氏物語』第十二帖「須磨」の巻において、名残を惜しむ宰相中将(頭中将)に対して光源氏が発した「雲ちかく飛びかふ鶴(たづ)もそらに見よ~」の歌あり。同じく『源氏物語』第十四帖「澪標」の巻において、光源氏からの御文に対して女君(明石の御方)が返した「数ならぬみ島がくれに鳴く鶴を~」の歌あり。[↩]






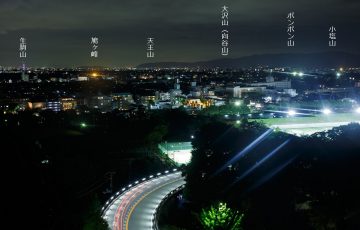























最近のコメント