2015年(平成27年)3月27日の日没時、黄色くライトアップされる京都タワーを眺めるため、久々に「大田の小径」を訪れました。
「大田の小径」は上賀茂の大田神社さんの裏山にあたります。
「大田の小径」を歩いた話や、古くは「太田山」(大田山)と呼ばれていたといった話は上の記事に。
道中、上賀茂神社さんや二葉姫稲荷神社さんの裏山にあたる「神宮寺山(じんぐうじやま)」の様子が昔とは変わっていることに気付き、そちらにも興味が湧きます。
すでに山中は薄暗く、満足に写真を撮影できそうにないため、27日は「大田の小径」ハイキングに留め、翌日、3月28日の夕方に上賀茂を再訪しました。
今回はその日の話を。

上賀茂神社さんの「御所桜」。
一重咲きの枝垂桜ですが、3月28日の時点ではつぼみが多く、まだこれからといった印象を受けました。
その後、気温が高い日が続いた影響で一気に開花が進み、30~31日あたりに満開となりましたが、すでに花期を終えています。
満開期の「御所桜」を撮影した写真は上の記事に。
2015年(平成27年)4月10日現在、八重紅枝垂の「斎王桜」が盛りですが、賀茂川堤防「半木の道」の八重紅枝垂と併せ、この週末が最終となるでしょう。
上賀茂神社さんから大田神社さんへ向かう道すがら、左手(北)、形の良い神宮寺山の姿がちらちらと見え隠れしていますが、撮影適地が見当たりません。
民家さん越しに撮影するのは避けたいと考えていたら、けっきょく、大田神社さんに着いてしまいました。
今回のコースとは無関係ですが、てっとり早く神宮寺山の山容を眺めたいということであれば、賀茂川に架かる御薗橋付近がお勧め。
御薗橋の右岸(西)から南に下がり、北東(上賀茂神社さんの方角)を向けば、賀茂川の対岸に鉢状の美しい丘陵の姿が目に入り、それが神宮寺山です。
大田神社さんに参拝後、拝殿の脇に見える「大田の小径」の案内標に従い、大田神社さんの西側の車道を北進。
左手(西)に神宮寺山の東斜面が見え、そのあたりの階段道(作業道)から入山できそうですが、ひとまず、前日の分岐まで登ります。
道標「1」までの道のりについては前回の記事を参照。

「大田の小径」道標「1」の分岐。小規模な峠。
北は小池、東は大田の小径、南は大田神社さん、西は神宮寺山。
「大田の小径」の取付にあたる分岐です。
北は「小池」(京都GC上賀茂コースのため、通行不可)、東は「大田の小径」(~岡本口)、南は大田神社さんへ。
西のみ道標がありませんが、写真でも後方に写っている看板が見え、そちらへ向かう踏み跡が見えます。
前日は東の「大田の小径」を登りましたが、西の神宮寺山の様子が気になり、翌日、つまり、この日、再訪したしだいです。
この地点を取付として、ひとまずは後ろに見える看板のあたりまで登ります。

「京都・文化の森(京の景観保全林・神宮寺山)」の案内看板。
夕方に撮影しており、西向きの木立越しに夕日が見えています。
この看板は大文字山を登っていらっしゃる方には見覚えがあるものでしょう。
法然院さんの裏山にあたる善気山にも「京都・文化の森」の看板が立っていますね。
あとは京北の山でも見かけた、ような。
また、宇治市の大吉山(仏徳山)にも同様の看板が立っています。
これは2003年(平成15年)より始まった整備事業で、世界文化遺産周辺の森での景観保全を目的としたものです。
神宮寺山は上賀茂神社さんの東の裏山にあたる約160m小ピーク。
かつて、その西麓には片岡社(片山御子神社)(現代においては上賀茂神社の摂社)の神宮寺(神社に付随する寺院)があり、さらに、その神宮寺の鎮守社として二葉姫稲荷神社がお祀りされていました。
その後、神仏分離により神宮寺は失われましたが、その鎮守社であった二葉姫稲荷神社さんは神宮寺山の南西腹に遷されました。
神宮寺の裏山であったことが「神宮寺山」の山名の由来ですが、古くは「片岡山」や「片岡森」、あるいは「鶴ヶ岡」とも呼ばれていました。
このあたりの山々は上賀茂神社さんの杜であり、現在では景観保全林として整備されています。
既存の踏み跡を辿るに留め、むやみに踏み跡を広げないほうがよいでしょう。
「神宮寺」
澤田社の東に有 [1]
片岡山の麓に有
十一面觀音を安置す
其前に池有
神宮寺の池と云
(後略)
『菟藝泥赴』
貞享元年(1684年)の『菟藝泥赴』 [2]では「神宮寺」について上のように述べています。
上の写真で看板の右遠方にテープが見えていますが、そのテープのあたりから急斜面を直登すれば数分で山頂です。
やや不明瞭ながら、足元のシダを分けるように踏み跡が付いていますので、それを辿ると分かりやすいでしょう。
ただし、このテープの地点から直登せず、斜面を南に巻くように水平に進み、岩場がちになったあたりから少し登れば展望地があります。
この展望地は下から見上げても気付きにくいですが、上から見下ろすと東向きが開けているのが分かります。
展望地については後述するとして、ひとまず登頂。

神宮寺山の山頂。上賀茂神社さんの裏山で片岡山とも。標高171m。京都市北区。
この山の山名については、京都市、上賀茂神社さん、ともに「神宮寺山」としていますので、旧称はともかく、まず、現在の呼称が優先されるべきだと考えます(現地現称主義)。
また、「片岡」の呼称は、神宮寺山でも西端域の阜(丘)に限定していた可能性があります。
話が長くなりすぎるのでほどほどにしておきますが、「片岡山」と「片岡森」を区別する考えもあり、それも影響している。
現行の地理院地図(地形図)では160m等高線の上ですが、現状では精度が高いと考えられる「基盤地図情報5mメッシュ(標高)」(5mDEM)では約170mであることから、実際の標高は170m近いと考えられます。
京都市の都市計画基本図では当地を指して「神宮寺山 171.0m」としていますので、当ウェブサイトでも標高171mを採用しておきます。
旧版の地形図から標高172mとしても良いでしょう。
地形図で見ると一目瞭然ですが、神宮寺山の山頂と呼べる地点はなだらかで広く、現地でも特定は困難です。
1961年(昭和36年)修正、1965年(昭和40年)発行の二万五千分一地形図「京都東北部」までは、上の写真の地点に標高点172mが表示されます。
1967年(昭和42年)改測、1971年(昭和46年)発行の二万五千分一地形図「京都東北部」からは標高点が消えていますが、おおむね写真に写るあたりを山頂と見なせばよいでしょう。
上の写真をよく見ると、木立の間、右に大文字山、左に比叡山が写っていますが、山頂からは京都タワーも見通せます。

神宮寺山の山頂からの展望。京都タワー、伏見桃山城を遠望する。
撮影地点から京都タワー(京都市下京区)まで8.2km。
神宮寺山の山頂は全面的に開けてはおらず、一部の向きのみ開かれていました。
大文字山や京都の街並みが見える向きに限って開けている理由は分かりやすいですね。
また、山頂から少し東に下ったあたりからは比叡山に対してのみ、これもピンポイントに開けています。
西から望むため、大比叡の山頂は分かりにくいものの、四明岳の山上の施設がよく目立ちます。

神宮寺山の山頂付近から「都富士」比叡山を望む。
常々申し上げていますが、京都の山は比叡山や愛宕山に対して開けている、故意に開いている山が多く。
比叡山は大比叡と四明岳の二峰から成る双耳峰ですが、上賀茂の山から眺めると、西の四明岳のみ目立って見えます。

山中にはミツバツツジ(三葉躑躅)のお花が咲いていました。
西日が差して綺麗です。
神宮寺山(あるいは大田神社さんの裏山)は北大路魯山人ゆかりの山でもあります。
幼い頃に手を引かれて登った神宮寺山で見た「真っ赤な山躑躅」が魯山人の原風景だそうですが、上の写真に写るのは赤いヤマツツジではなく、紫色のミツバツツジです。
登りに利用したシダの中を歩くコースから外れ、わずかにその南寄りの斜面を下ると、やや開けた岩場があることに気付きます。
そのあたりだけ故意に踏みならされており、ちょっとした展望地となっているようです。
山頂からは大文字山の字跡が見通せる程度でしたが、この場所からは大文字山から京都東山方面にかけて見晴らしがよく。

神宮寺山の展望地から大文字山、京都東山、醍醐山地を望む。
| 主な山 | 距離 | 標高 | 山頂所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大文字山 | 6.7km | 465.2m | 京都市左京区 | |
| 西千頭岳 (千頭岳三角点峰) | 14.7km | 601.7m | 京都市伏見区 | |
| 高塚山 | 13.3km | 484.9m | 京都市伏見区 | |
| 醍醐山 | 14.7km | 454m | 京都市伏見区 | |
| 大峰山 | 22.8km | 506.2m | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 最高点は約510m |
| 清水山 | 8.1km | 242.1m | 京都市東山区 |
昨年から今年にかけても千頭岳や醍醐山を何度か登っていますが、当ウェブサイトでは一度も取り上げていません。
何点か山行記録を残しておきたいと考えていますが、いかんせん時間が足りず。

神宮寺山の展望地から清水山、清水寺さん、青龍殿(青蓮院門跡 将軍塚大日堂)などを望む。
知恩院さんや祇園閣(大雲院さん)、京都大学さんの花山天文台なども写っています。
清水山から阿弥陀ヶ峰にかけて東山の連なりの遠方に見えているのは、山城地域でも井手町、和束町、木津川市あたりの山々ですが、ピークの見定めはなかなか難しく。
左遠方に写る「大峰山」は宇治田原町の山。
歩いてみて分かりましたが、「大田の小径」だけではなく、神宮寺山もなかなか好展望の山でした。
上賀茂神社さんや、地元の方の山であって、いわゆるハイキングのための山ではないでしょうが、ちょっとした息抜きで大文字山や京都タワーを眺めるには良さそうです。
また、この神宮寺山(片岡山)を含む山域は、かつては「賀茂山」と呼ばれていたり、あるいは和歌に詠まれた「賀茂の神山(かみやま)」である可能性があります。
その話は過去の記事で。
神宮寺山(地理院 標準地図)
「神宮寺山(ジングウジヤマ)(じんぐうじやま)」
標高171m
京都市北区
「上賀茂神社(賀茂別雷神社)」
京都市北区上賀茂本山 付近










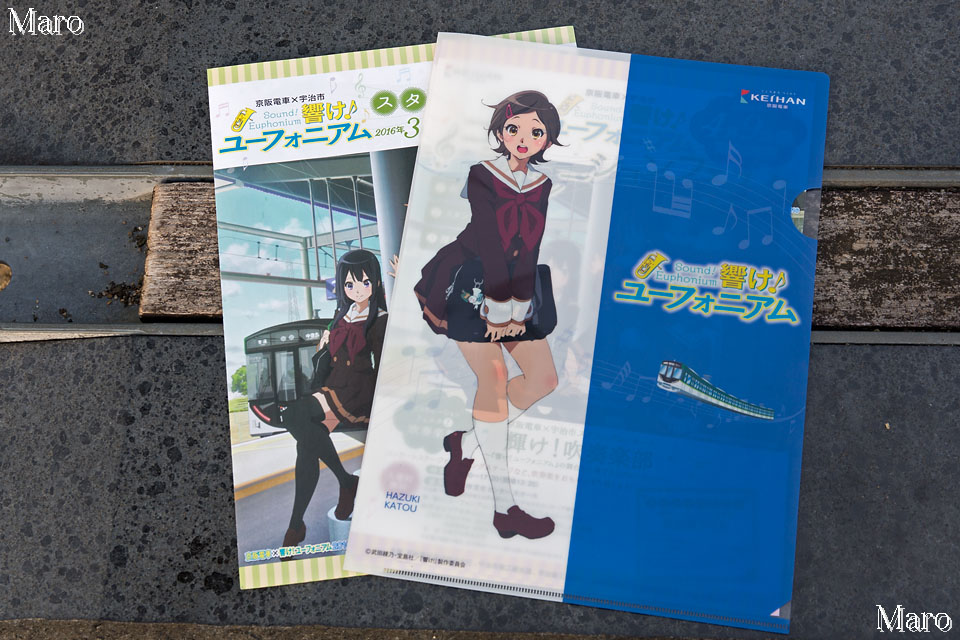





















最近のコメント