落雷の当日、いち早く、前回のタシロランの記事に追記しておきましたが、改めて個別の記事としておきます。
2014年(平成26年)7月19日14時45分頃、大文字山の火床、弘法大師堂(弘法さんの祠)付近に雷が落ちました。
火床の真ん中からのぼる白煙に下から気付いた方もいらっしゃるでしょうが、幸いにも山火事として広がるようなことはなく。
大文字山の火床に落雷

霹靂の爪痕。大文字山火床の弘法大師堂。左に金尾(かなわ)。
舗装された地面の一部を砕きましたが、お堂そのものは無事でした。
雷の威力は凄まじいものがありますが、弘法さんのご加護もなかなかのものです。
これだけでは殺風景ですので、今日、撮影したお花の写真も1枚だけ……。
ヤブカンゾウのお花

ヤブカンゾウ(藪萱草)のお花。広義のワスレグサ。
ユウスゲやゼンテイカ(ニッコウキスゲ)などと比較すると、どこか暑苦しく野暮ったい印象を受けるため、あまり好まれないようですが、個人的には美しい造形だと思います。
池の谷地蔵さんのイヌさん 池の谷薬草園

梅雨明けの日、如意ヶ岳の奥深く、雨社さんや池の谷地蔵さんにお参り。
雨社は雨神社や雨ノ宮神社とも、池の谷地蔵は池地蔵や池の地蔵とも。
池の谷地蔵さんでは、よほど退屈で暇を持て余していたのか、私を見るなり犬が駆け寄ってきました。
よく吠えた先代のイヌさんと異なり、当代のイヌさんは(普段は)おとなしく、誰にでもなついていますが、なぜだか私にはあまりなついてくれません。
それなのに、珍しく、今日は私を押し倒さんばかりの勢いで向かってきました。
この当代のイヌさんの名前が「○○ちゃん」であることは存じていますが、漢字で記すと「○ちゃん」なのか、あるいは「○ちゃん」なのか、こちらの尼さん(庵主さん)とは挨拶を交わす程度ということもあり、詳しいことは分かりません。
そもそも、先代の名前も同じ「○○ちゃん」だった記憶が……。
あと、当代さんは「普段は」おとなしいですが、ゲートが閉じられた後の時間帯に、不用意に池の谷地蔵さんに近づくと、とんでもなく吠えてきますので、番犬としては優秀だと思います。
そうそう、雷も恐ろしいですが、夏の山で怖いのがスズメバチ。
今日は大文字山の三角点で1匹、大の字の左はらいの下部で1匹、スズメバチを見ました。
ご注意を!
以上、2014年(平成26年)7月21日の話。
追記
「高解像度降水ナウキャスト」について
本題とは無関係ですが、気付く方は気付くでしょうから、こちらに追記しておきます。
2014年(平成26年)8月7日、気象庁さんにより、降水域の分布を高い解像度で解析・予測する「高解像度降水ナウキャスト」の提供が開始されます。
アドレスは7日13時頃に一般公開される見込みですが、実は、すでにアクセス可能です。
「高解像度降水ナウキャスト」
http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/
マルチデバイス対応で、スマートフォンからの操作にも対応しています。
一定の知識があれば、かなり早い段階で掘れましたが、公開前にアドレスが筒抜け状態だったのは問題かもしれません。
追記。
久々に確認したらアドレスが変わってますね。
「高解像度降水ナウキャスト」
https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/
こちらからアクセス可能です。
追記終わり。
「○○ちゃん」について
本記事の後日談として、公開して少し後、庵主さんの旦那さんとお話しする機会があり、イヌさんの名前、「○○ちゃん」の漢字表記についてお尋ねしてみました。
とくに決まっていないが、しいて挙げれば「○ちゃん」だそうです。
名前の由来や、詳しいお話も伺いましたが、こちらに書くのは控えておきます。
(本記事において、初稿の公開時はイヌさんの名前を出していましたが、思うところがあり、伏せておきます)
比叡三郎
後年、瓜生山に落ちたと思われる雷を動画で撮影した記録は上の記事に。
大文字山(地理院 標準地図)
「大文字山(ダイモンジヤマ)(だいもんじやま)」
標高465.2m(三等三角点「鹿ケ谷」)
京都市左京区(山体は山科区に跨る)






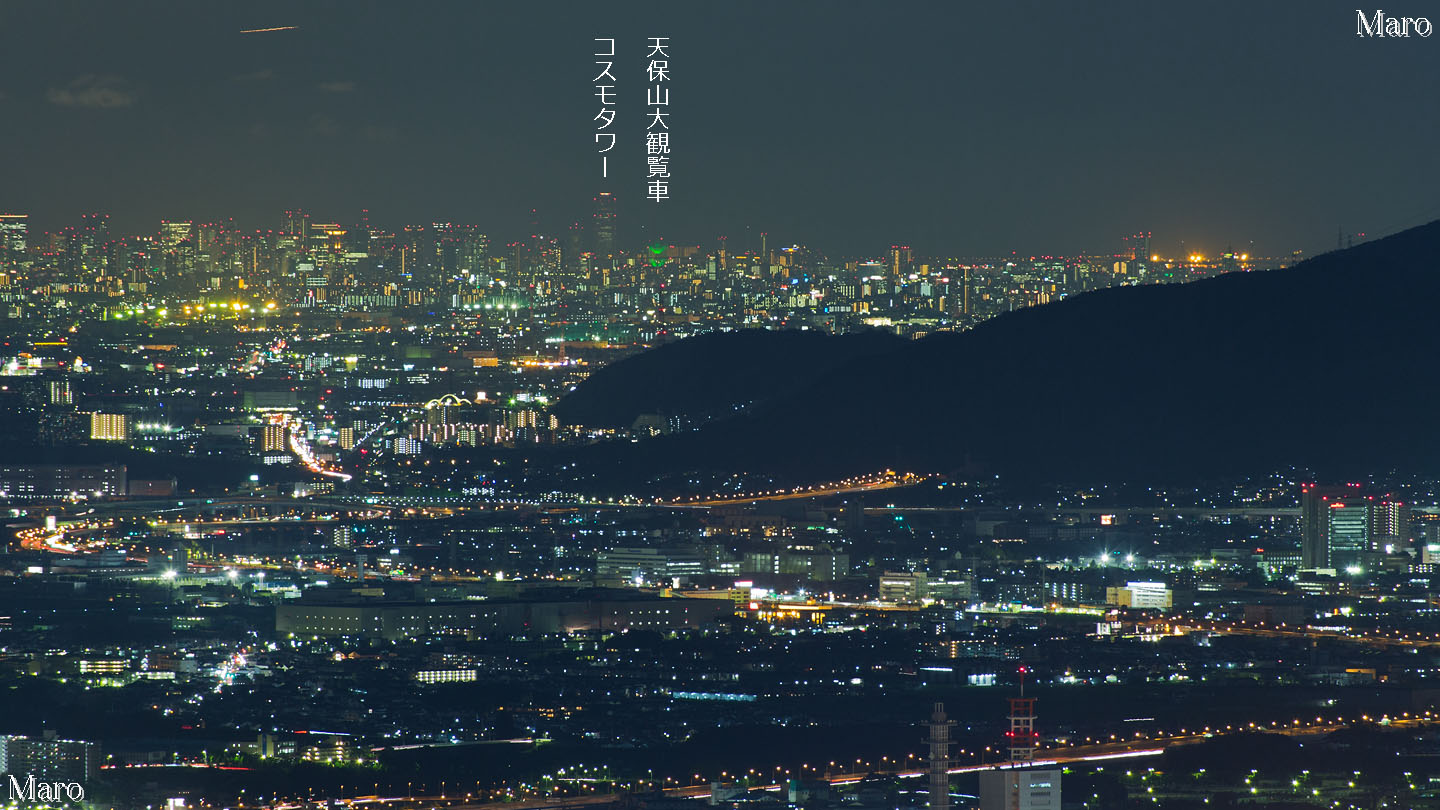























最近のコメント