一瞥しても意味が分からない記事のタイトルですが、昨年末、2015年(平成27年)12月30日の話。
ちょっとした思い付きで嵐山を訪れましたが、渡月橋の付近は大混雑。
人混みを避けるように、いわゆる観光地としての「嵐山」(嵐山公園の周辺)でも桂川(大堰川)の右岸、あるいは山としての「嵐山」(嵐山城跡の周辺)の山麓に所在する「嵐山虚空蔵」法輪寺さんを訪れました。
法輪寺さんは京都では貴重な「ひつじの山」でもあり、お花見がてら、2015年(平成27年)3月にも訪れています。
未年も終わりということで、境内のヒツジさんにご挨拶を。
目次
法輪寺 羊の像? 山羊の像?

「嵐山虚空蔵」法輪寺さんの羊像? 山羊像? に、未年最後のご挨拶。
よく見ると、ヒツジさんの遠方に沢山などの特徴ある山並みが写っています。
ちょうど、法輪寺さんにいらっしゃった若い方々が、ヒツジさんの像を見て、「これって羊?」「いや山羊では」「でも羊の寺だって」といった会話をなさっていました。
実のところ、私もヒツジさんかヤギさんか分かりませんが、そもそも、未年の「未」はヒツジを指しているのか、ヤギを指しているのか曖昧です。
英語でも、”Year of the goat”、つまり、「山羊の年」の表記が一般的で、”Year of the sheep”、「羊の年」の表記は珍しく。
未年の羊を表すにあたり、中国でもヒツジさんではなくヤギさんらしき動物の絵を描く方が多いところを見ると、古くよりヒツジとヤギが混同されていたのでしょうか。
追記しておきますと、これはおそらくヒツジさんだろうとのことです。
法輪寺 舞台からの展望・眺望
申年の比叡山、一本杉を望む

嵐山・法輪寺さんの舞台から「都富士」比叡山を望む。空を舞うトビ(鳶)。
撮影地点から比叡山四明岳(京都市左京区)まで15.1km。
京都市側から見て、比叡山の向こうが大津市の坂本です。
写真の右端に一本杉の送信塔施設や登仙台、叡山閣の周辺が見えていますが、かつて、一本杉や夢見が丘(昔の「青山」)のあたりは峠の要所でした。
京都の白川村から山中を経て近江の志賀へ至る昔の峠道としては、いわゆる「志賀越道」がよく知られています。
田ノ谷峠(田の谷峠)を乗り越えて南志賀へ至るコース(現代の「山中越」)とは異なり、往時の「山中越」は、山中から志賀峠(現代では比叡山ドライブウェイの下)を乗り越え、崇福寺や志賀の大仏を経て滋賀里や唐崎へ下る道のりでした。
この「山中越」や「今道越」と、「志賀山越」を同一視する説がインターネット上では広まっていますが、それぞれがどこを指すかは時代や史料により異なるため、厳密に申し上げれば誤りです。
京都側から見て、一本杉を越えた山の向こう、近江坂本には神猿さんで知られる日吉大社さんが鎮座します。
年末の時点では年始にどの山を登るか決めかねており、候補として、申年の神社と言える日吉大社さんをお参りし、その裏山たる比叡山(か八王子山)から初日の出を眺めるのもいいか、と考えていました。
結果的には小倉山からご来光を拝むことになりましたが……。
志賀の山越と今道越
興味を持つ方もいらっしゃるようなので、「志賀の山越」について補足しておきます。
顕昭による『古今和歌集集』(古今集)の注釈書『古今集註』(顕昭古今集註)では、紀貫之の歌の詞書に見える「志賀山越」(志賀の山越)について、
是ハ如意越ヨリハ北 今路越ヨリハ南ニ 志賀ヘ越ル路アリトイヘリ
『顕昭古今集註』巻二
としています。
「志賀ヘ越ル路」は「今道越」や「如意越」とは異なるコースであり、かつ、その両道の間に挟まれたコースだと分かります。
顕昭は平安時代末期~鎌倉時代初期の人で、鎌倉時代には「志賀ヘ越ル路」は伝聞の過去形(アリトイヘリ)で語られる存在だったようです。
この「志賀ヘ越ル路」が、歌枕に見える「志賀の山越」で、今路越より南、如意ヶ岳を越える道(=如意越)より北に所在したことが伝わります。
廃れてしまった「志賀の山越」ではなく、「今道越」が山中から坂本へ抜けるコースとして利用されていたことが、後世の史料からも読み取れます。
たとえば、享保4年(1719年)の『京城勝覧』では、京都の白川村から山中を経て、近江の東坂本へ観光に出向く道のりについて述べています。
白川村から山中に至って、「志賀の山越は右の方にあり。むかし道なり。今坂本にゆくには新道を通る」とあり、この新道の峠を「今道のたうげ」としています。
『京城勝覧』では、「むかし道」である「志賀の山越」と、「新道」「今道の峠」を別のコースと見なしていることは明らかです。
京都側(西)から見て、むかし道(志賀の山越)が右で、新道(今道)が正面か、あるいは左ですので、これは『顕昭古今集註』の「今路越ヨリハ南ニ 志賀ヘ越ル路アリトイヘリ」の描写とも一致します。
新道(今道の峠)が具体的にどのコースや峠を指しているのか分からないのが惜しいですが、志賀峠を越えるコースを選んだのでしょうか。
貞享3年(1686年)の『雍州府志』でも、「志賀山越在二山中越南一」(志賀の山越は山中越の南にある)とあり、「志賀の山越」が山中越の南にあることが読み取れます。
『太平記』における「今道越」を見てみると、坂本や比叡山の官軍が京都に攻め入る際、新田義貞が「今道越」を利用して京都に入り、北白川に陣取っています。
新田左衛門督兄弟は二万餘騎の勢を卒し今道より向て北白川に陣を取る
『太平記』巻第十五
北畠顕家は大津から東海道を経て山科に陣取り、楠木正成らは「西坂」(雲母坂)を下って下松(一乗寺)に陣取っています。
坂本に居た新田軍が「北白川に陣取る」には、「今道越」を利用するのが最適であることが窺えます。
搦手には仁木細川今川荒河を大將として四國中國勢八萬餘騎今道越に三石の麓を經て無動寺へ寄んと志す
『太平記』巻第十七
逆に、足利軍が比叡山を攻める際にも「今道越」の名前が見えます。
「志賀の山越」ではなく、「今道越」と明示していますので、やはり、『太平記』の成立時期にも「今道」が利用されていたことが分かります。
ただし、先にも述べたように、「志賀越道」「山中越」「今道越」がそれぞれどこを指すかは時代や史料により異なるため、同じ呼称だからといって、必ずしも同じ道のりを指すとは限らないことに留意する必要があるでしょう。
加えて、「白鳥越」(史料によっては「白取越」の表記も)や「青山越」との混同も見られ、推測はできても、どれが正しいと断定するのは難しく。
史料によっては「むかし道」と「如意越」の混同や、あるいは「志賀山越」と「如意越」を同一視する描写まで見られます。
この件については、上の記事でも取り上げています。
今回の記事と合わせて目を通していただければ。
申年の京都東山・阿弥陀ヶ峰を望む

嵐山・法輪寺さんの舞台から京都東山・阿弥陀ヶ峰、清水寺さん、京都タワーを望む。
| 主な山、建築物 | 距離 | 標高 (地上高) | 山頂所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 音羽山 | 16.4km | 593.0m | 京都市山科区 (滋賀県大津市) | |
| 西千頭岳 (千頭岳三角点峰) | 17.5km | 601.7m | 京都市伏見区 | |
| 清水山 | 10.3km | 242.1m | 京都市東山区 | |
| 阿弥陀ヶ峰 | 10.1km | 196m | 京都市東山区 | 豊国廟 |
| 京都タワー | 7.9km | (131m) | 京都市下京区 |
この日、法輪寺さんを訪れた目的のひとつとして、見晴らしの良い舞台から東山の阿弥陀ヶ峰を望むことにありました。
阿弥陀ヶ峰の山上には太閤秀吉さんゆかりの豊国廟がお祀りされていますが、失礼ながら、秀吉さんといえば良くも悪くも「サル」のイメージが定着しています。
加えて、阿弥陀ヶ峰の山麓に所在する新日吉神宮さんは、近江坂本の日吉大社さんとの関わりが深く、やはり、神猿さんで知られます。
豊国廟と新日吉神宮さん……、そう考えると、阿弥陀ヶ峰もお猿さんと関わる申年の山と言えるでしょう。
新年を迎えたら阿弥陀ヶ峰を登ろうと考え、その前に、去る未年の山から来る申年の山を遠望、撮影しました。
元日に阿弥陀ヶ峰を登った話は上の記事に。
岩田山と虚空蔵山と松尾山
余談ながら、以前から私は法輪寺さんの裏山の呼称、山名を知りたいと考えていました。
法輪寺さんの付近の山腹には猿山として知られる「嵐山モンキーパークいわたやま」が所在しますが、他の方々からお話を伺うかぎり、「岩田山」は法輪寺さんの裏山のピークを指す呼称ではないようです。
最近になり、(山としての)嵐山と松尾山の間の山、つまり、法輪寺さんの裏山を「虚空蔵山」と呼んでいたことを知りました。
「虚空蔵山」を撮影したとされる古い写真を照査、検討するかぎり、地形図ではこの小ピーク だと考えられます。
呼称としてはきわめて適切ですが、その南東の松尾山(三角点275.6m)と近すぎるため、山名として廃れてしまったのかもしれません。(→「測地成果2024」により、三等三角点「松尾」の標高は275.5mと改定)
この「虚空蔵山」(推定)と松尾山の間は見晴らしが良く、(山としての)嵐山界隈では優れた好展望地となっています。
本記事をなぞっただけに過ぎませんが、この件は上の記事でも触れています。
愛宕山と鳥居形を望む

嵐山・法輪寺さんの舞台から愛宕山、五山送り火「鳥居形」の字跡を望む。
撮影地点から愛宕山(京都市右京区)まで6.8km。
やや分かりにくいですが、写真の手前に京都五山送り火「鳥居形」の火床が写っています。
写真の中央付近、愛宕山の東の中腹をよく見ると、山上の月輪寺さんが写っていますね。
その奥に竜ヶ岳の山頂付近のみ見える可能性がありそうですが、どうも手前の木立に遮られているようで、ピークの特定は困難です。
月輪寺を望む

「嵐山虚空蔵」法輪寺さんから「鎌倉山」月輪寺さんを望む。
月輪寺さんの下の谷筋は2本とも恐ろしく険しいですね。
写真では左寄りの谷は大杉谷の北東の谷で、大杉谷ではありません。
左下の隅で見切れているのが大杉谷の一部です。
法輪寺さんに参詣後、「虚空蔵山」を登ろうと考えており、ハイキングの準備も整えていましたが、あいにく、緊急の用件で呼び戻されたため、この日の山歩きは諦めました。
ですが、お猿さんに導かれるように、元旦、嵐山を再訪したのも何かの縁でしょう。
法輪寺(地理院 標準地図)
「法輪寺(嵐山虚空蔵)」
京都市西京区嵐山虚空蔵山町・嵐山中尾下町 付近











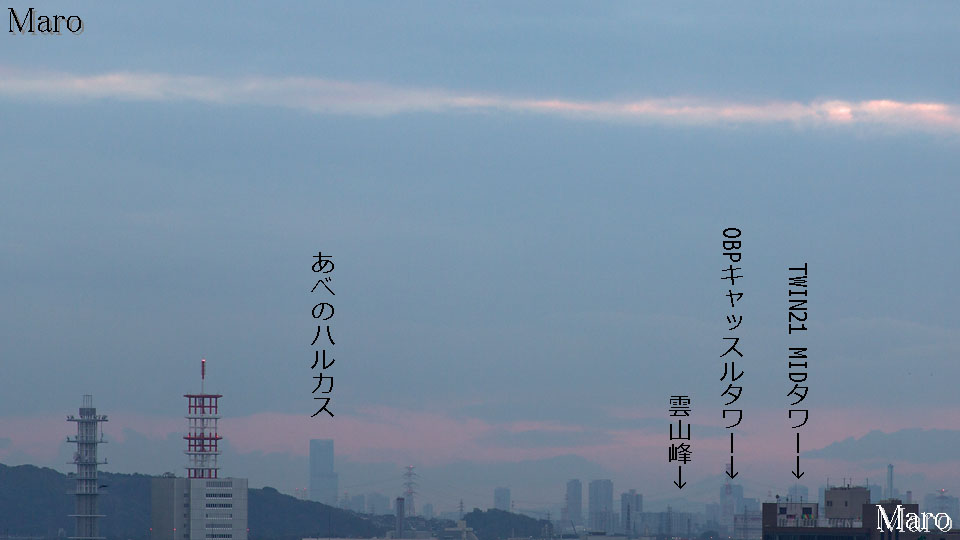




















最近のコメント